ブックカバーチャレンジ
|
パンデミックで「ステイホーム」の沙汰となり、 多くの人たちが自主的に自粛して経済は萎縮、 取り立てた税金をただ「還付」すればいいものを、 政府行政は「給付」と称してトンネル会社に流し、 遅れに遅れて失業と倒産が相次ぐも屁の河童らしく 世の中に大変なストレスが溜まっている昨今です。 医療、介護、保育、生産、物流など 命がけで出社して働いている方々の横で、 夜な夜なキャバクラに通う男子や ホストクラブの客引きに付いていく女子が 首都圏の新型コロナ感染者数を下支えし、 その他の一般市民は近所のジョギングか テレワーク後の散歩で憂さ晴らし。 SNSではいろいろなチャレンジが流行ってます。 これは、昭和でいう「不幸の手紙」、 平成でいう「テレフォンショッキング」みたいなもの。 抗議やチャリティなどを名目に、 テーマとなる画像や動画、 たとえばバケツに入れた氷水を頭から被る といったものをアップして、リレーしていく。 社会的な影響力のある有名人が加わるのが味噌で、 どれだけのセレブが登場するかが勝負。 これを、「ステイホーム」のみぎり、 特段社会的な影響力も扇動力もない一般市民が 真似して遊んでいるわけです。 僕に巡って来たのは「7日間ブックカバーチャレンジ」というやつ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー 誰が決めたルールかは存じませんが、 7日間毎日次の人を紹介するわけですから 実効再生産数=7という恐ろしい感染率。 SNSは無言の同調圧力も生じかねず、 「チャレンジ疲れ」もバラ撒きかねず、 ここは勝手な解釈で大いに楽しませて頂きました。 以下、記念に写しておきます。 2020年5月10日
知る人ぞ知る文芸界の隠れアイドルポアール・ムース森山さんからのバトン; 1日目:「人間の建設」  2020年5月11日
2日目:「ダライ・ラマ 科学への旅」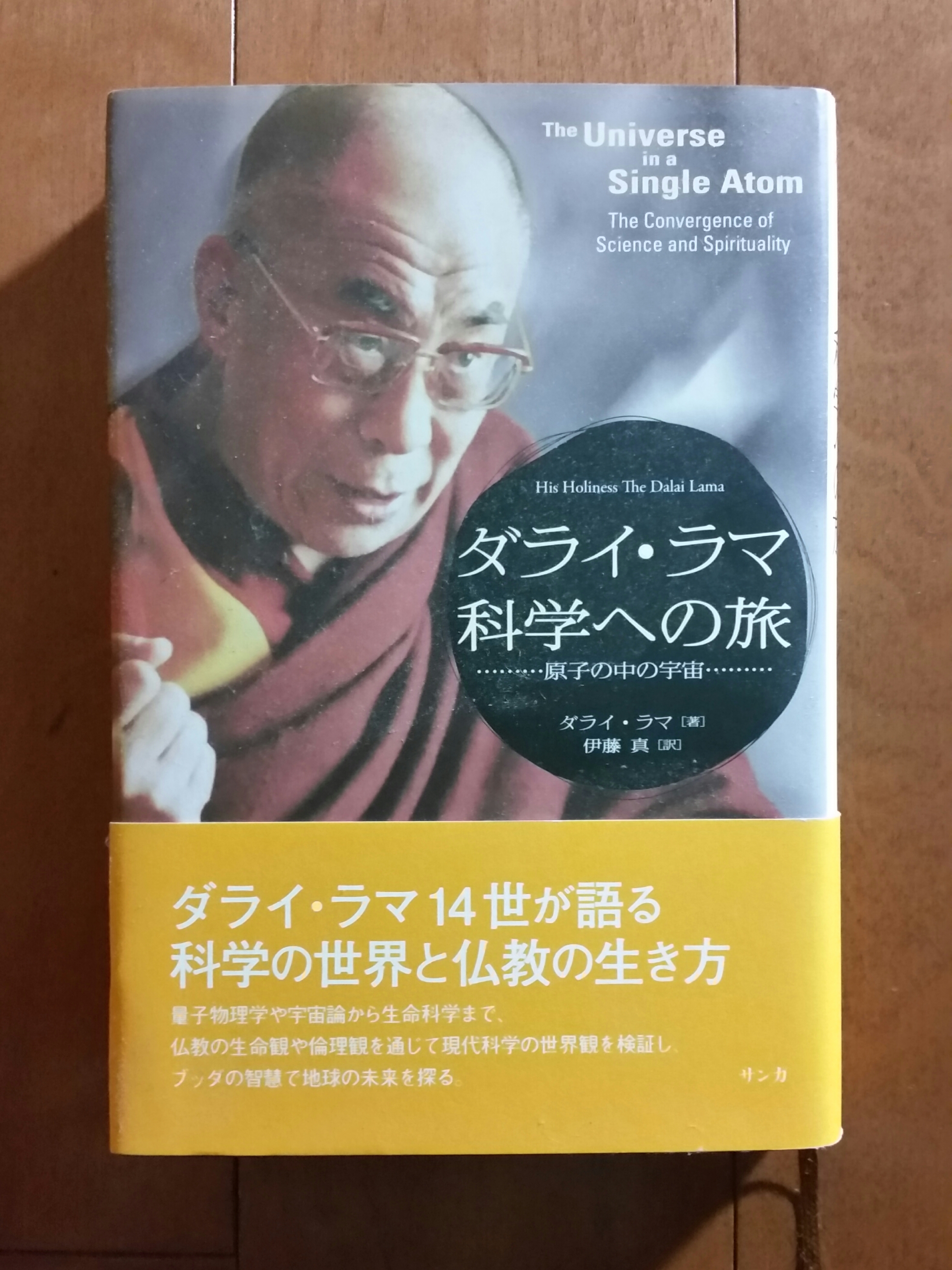 2020年5月12日
3日目:「おちおち死んでられまへん」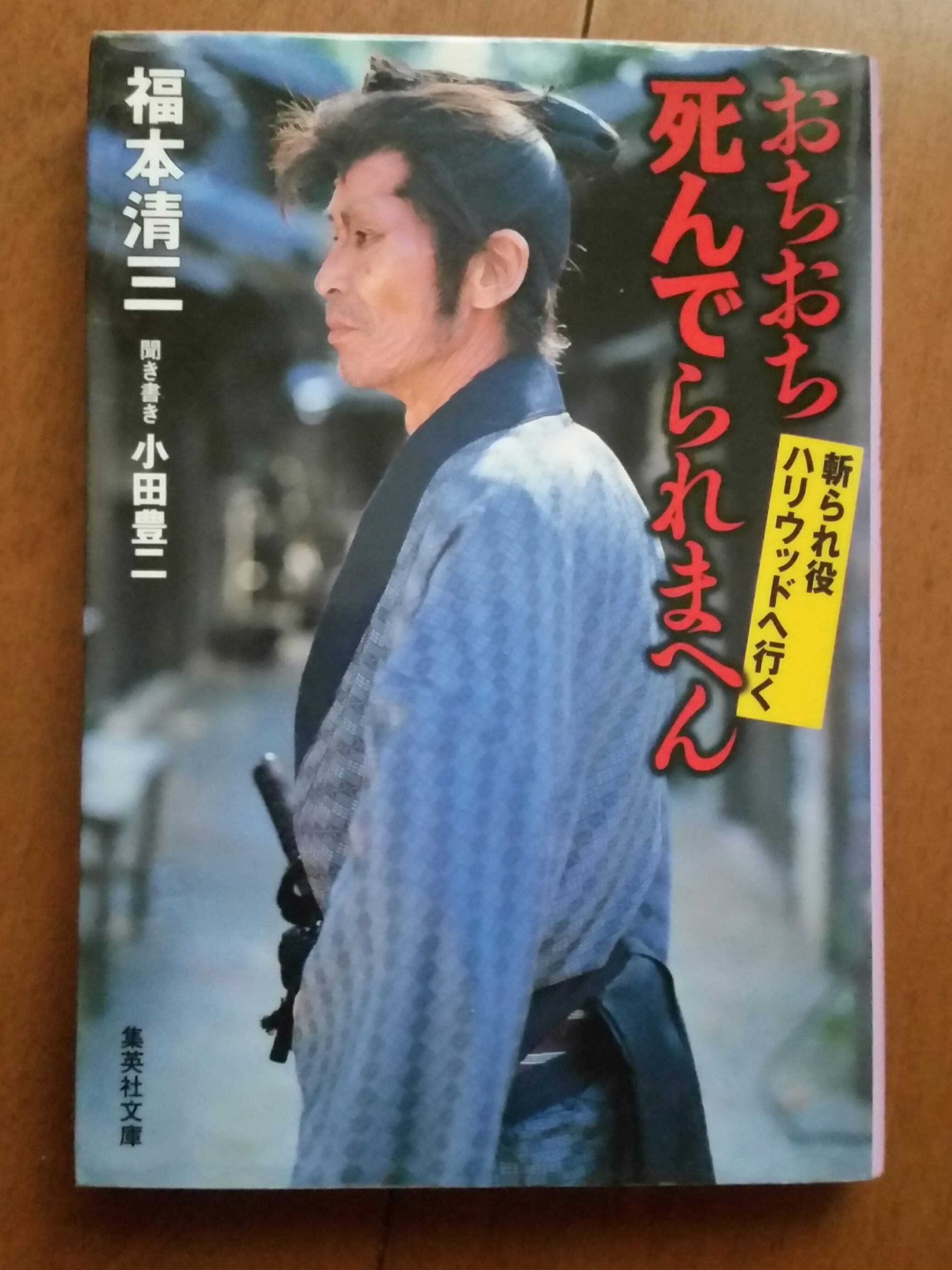 2020年5月13日
4日目:「21世紀の歴史」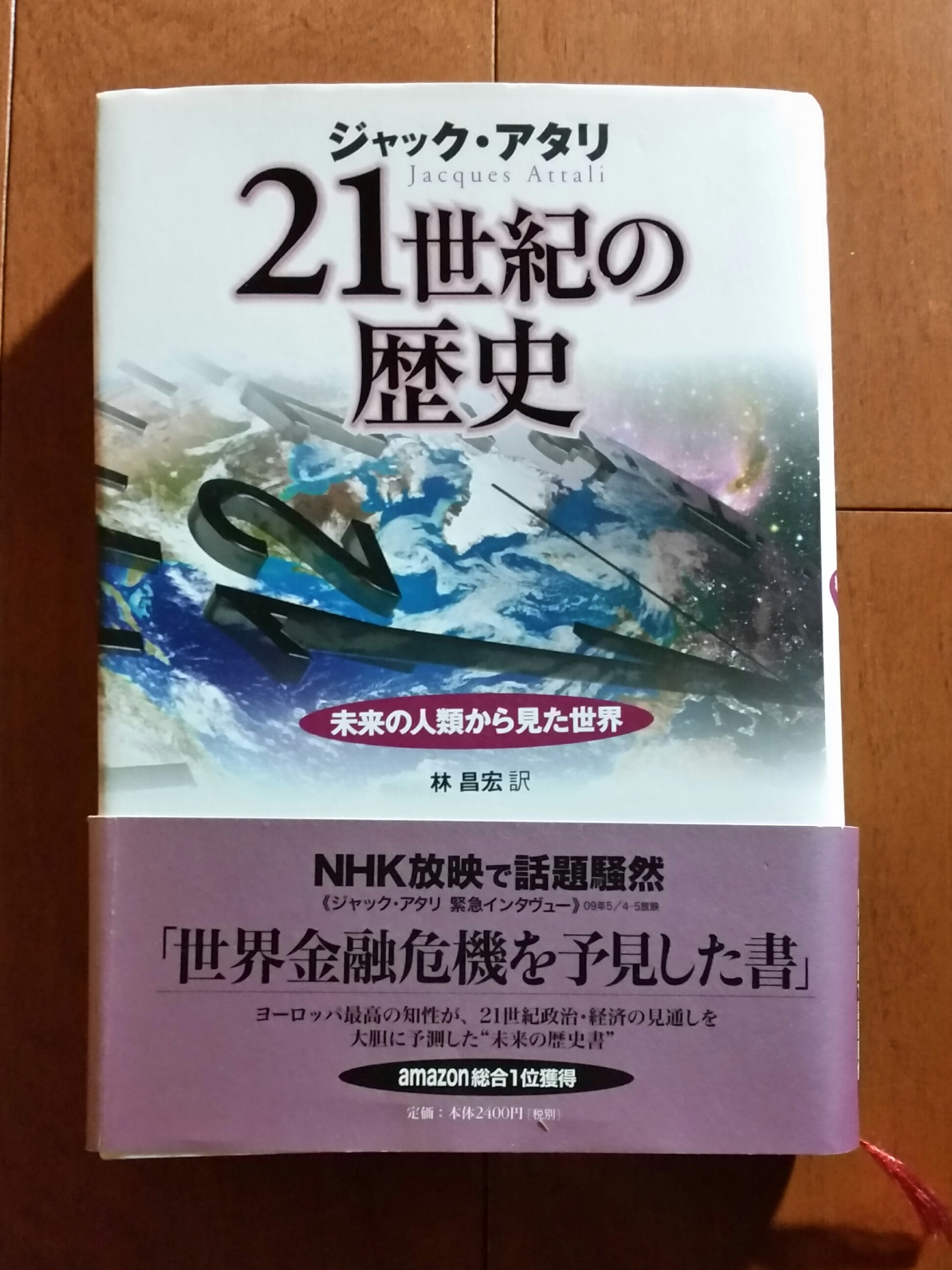 2020年5月14日
5日目:「アンヌへの手紙」 2020年5月15日
6日目:(自伝2作) 2020年5月16日
7日目: 小泉文夫フィールドワーク「人はなぜ歌をうたうか」  2020年5月22日
8日目:「オーケー! ボーイ」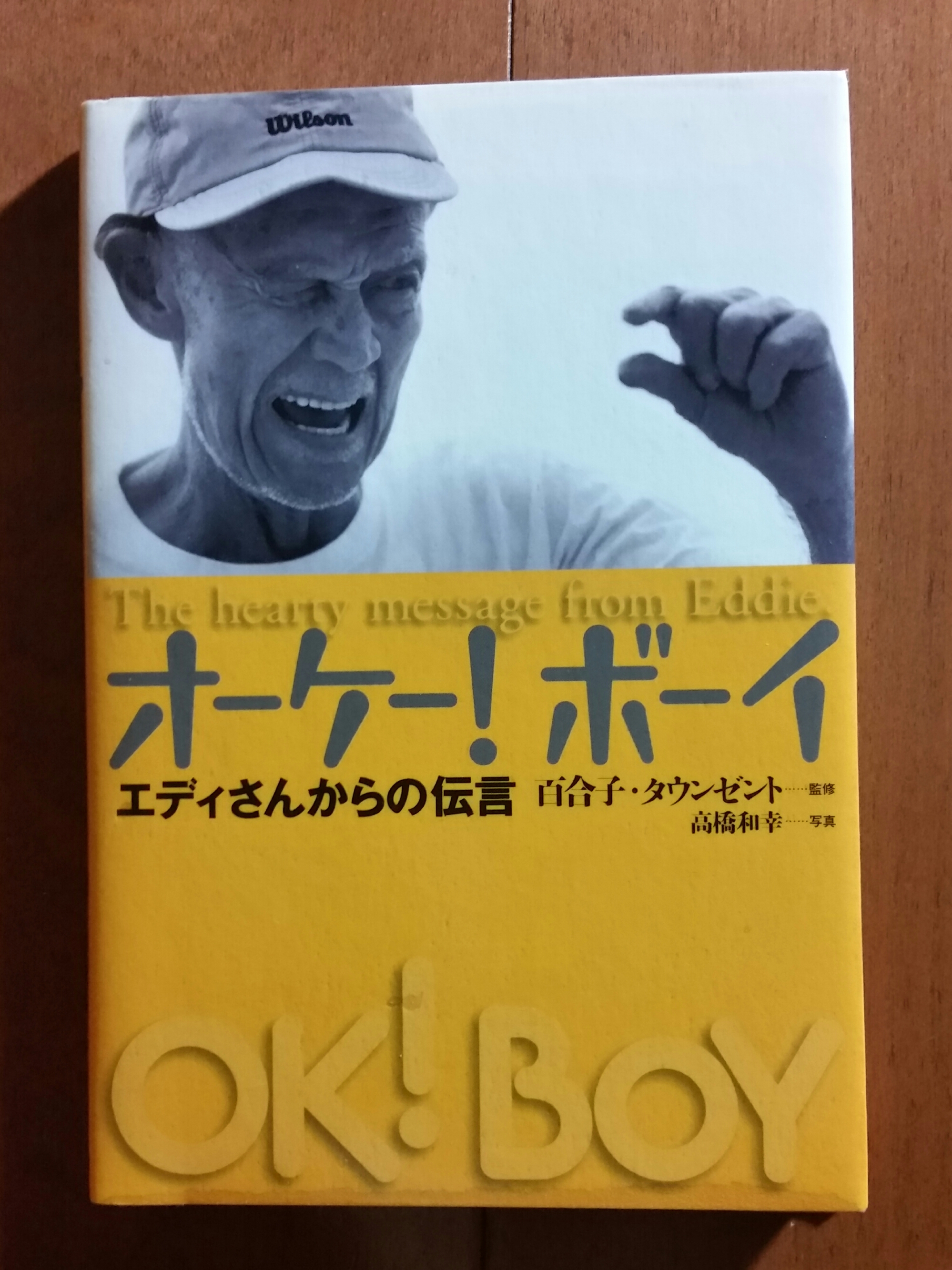 2020年5月23日
9日目:(木村元彦のサッカードキュメント) オシムのチームには、想像を遥かに超え、サッカーの妖精と称された選手もいました。彼のプレイは、引退後も・・・相手ゴールキーパーがハーフウェイライン近くのタッチ外に蹴り出したボールを、ベンチから飛び出し、ボレーで蹴り返し、しかも相手ゴールに入れてしまったスーツ姿の男がいました。当時名古屋の監督を務めていたドラガン・ストイコビッチです。一発レッドカード、退場!後のインタビューにこう応えてます。「悪気はなかったんだ。反省してるよ・・・でも、いいゴールだったでしょう?」 2020年5月25日
10日目:「ゲームのルール」 2020年5月26日
11日目:「奥さまは魔女」よ、永遠に 2020年5月27日
12日目:「日本語の謎を解く」 「コッテウシて、どういう意味や?」 「そりゃ、雄(オン)の牛のことや」 2020年5月28日
13日目:「迷える者の禅修行」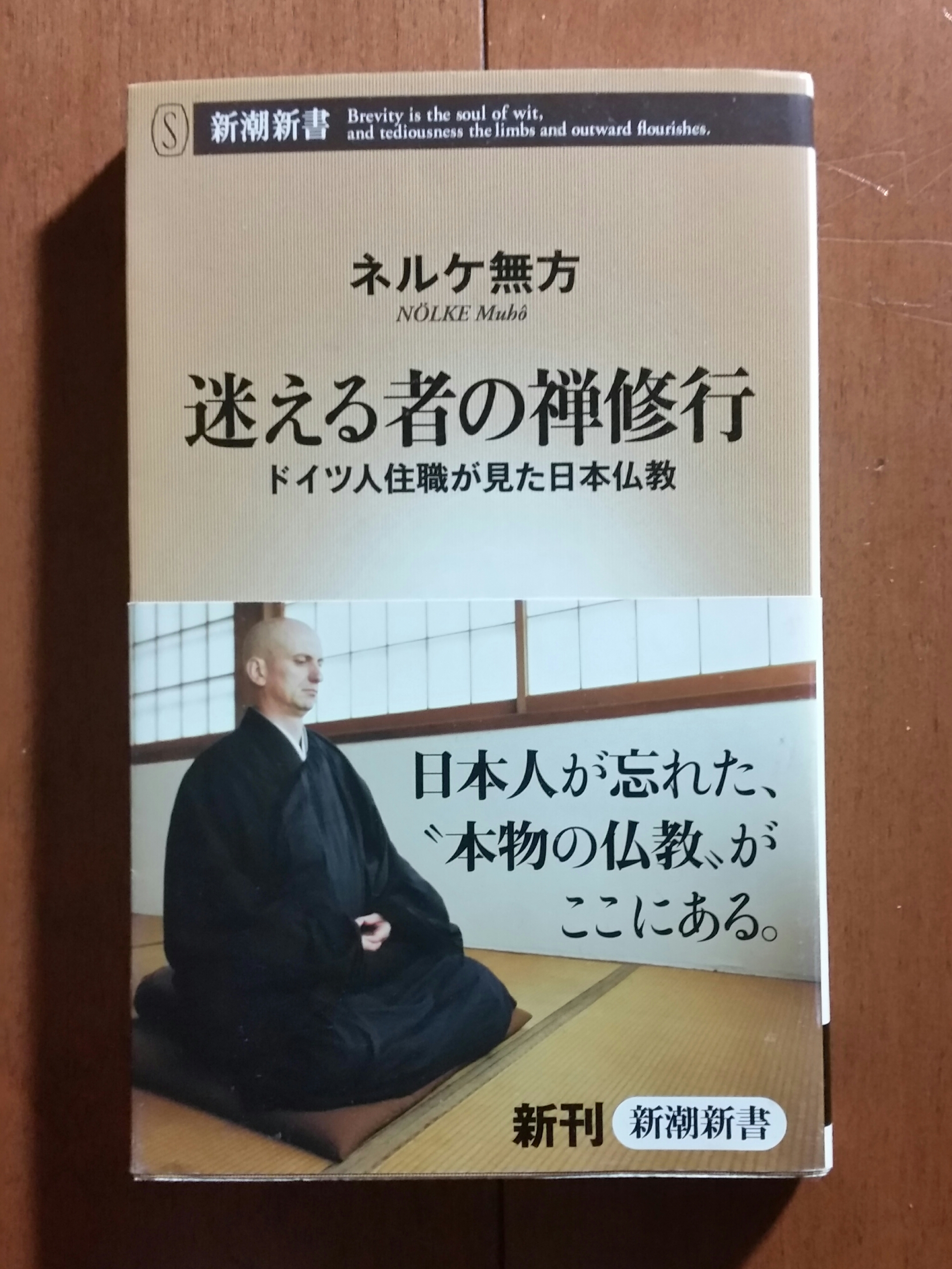 2020年5月29日
14日目:「第三の波」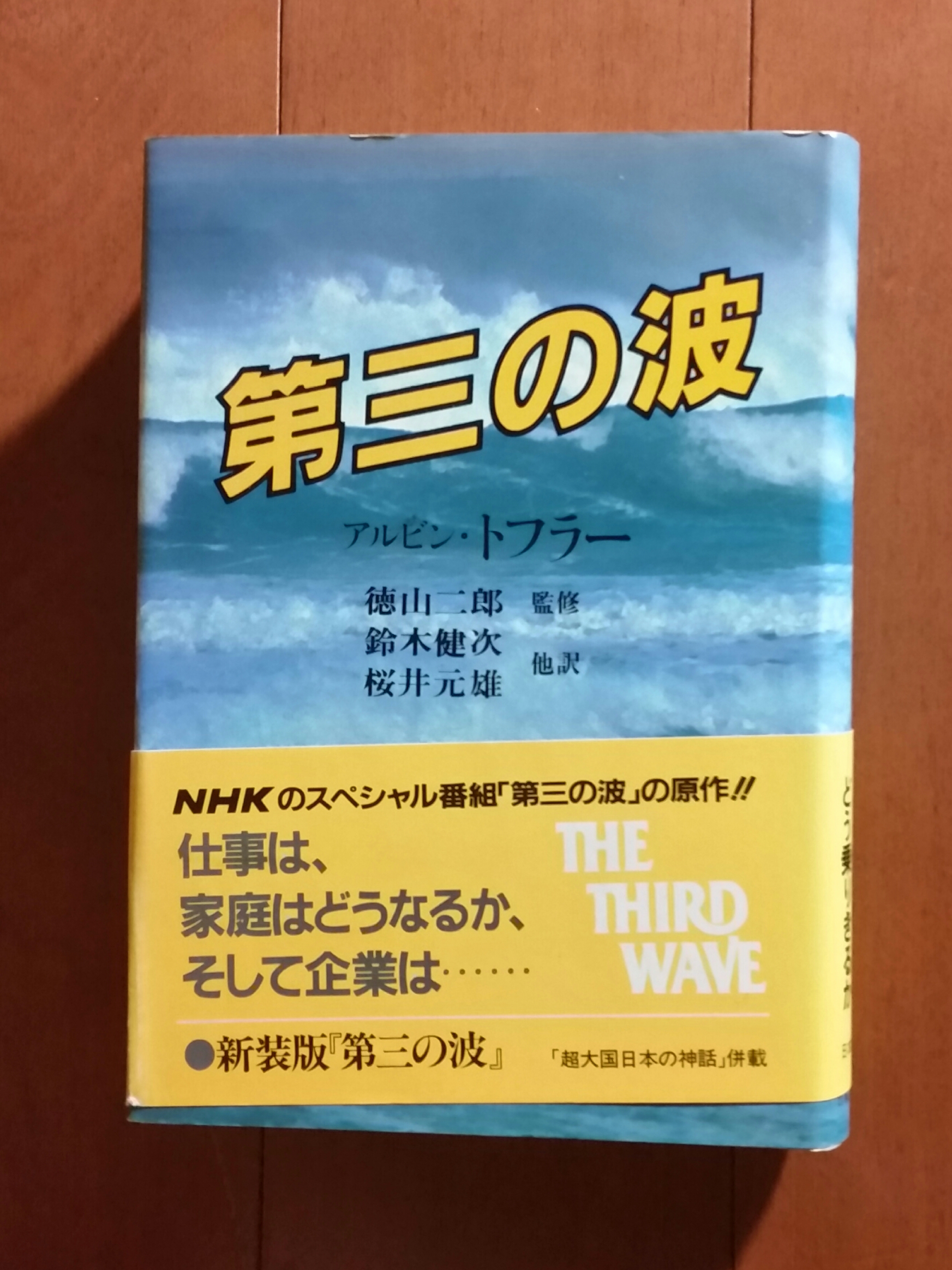 2020年5月30日
15日目:「スティーブ・ジョブズ」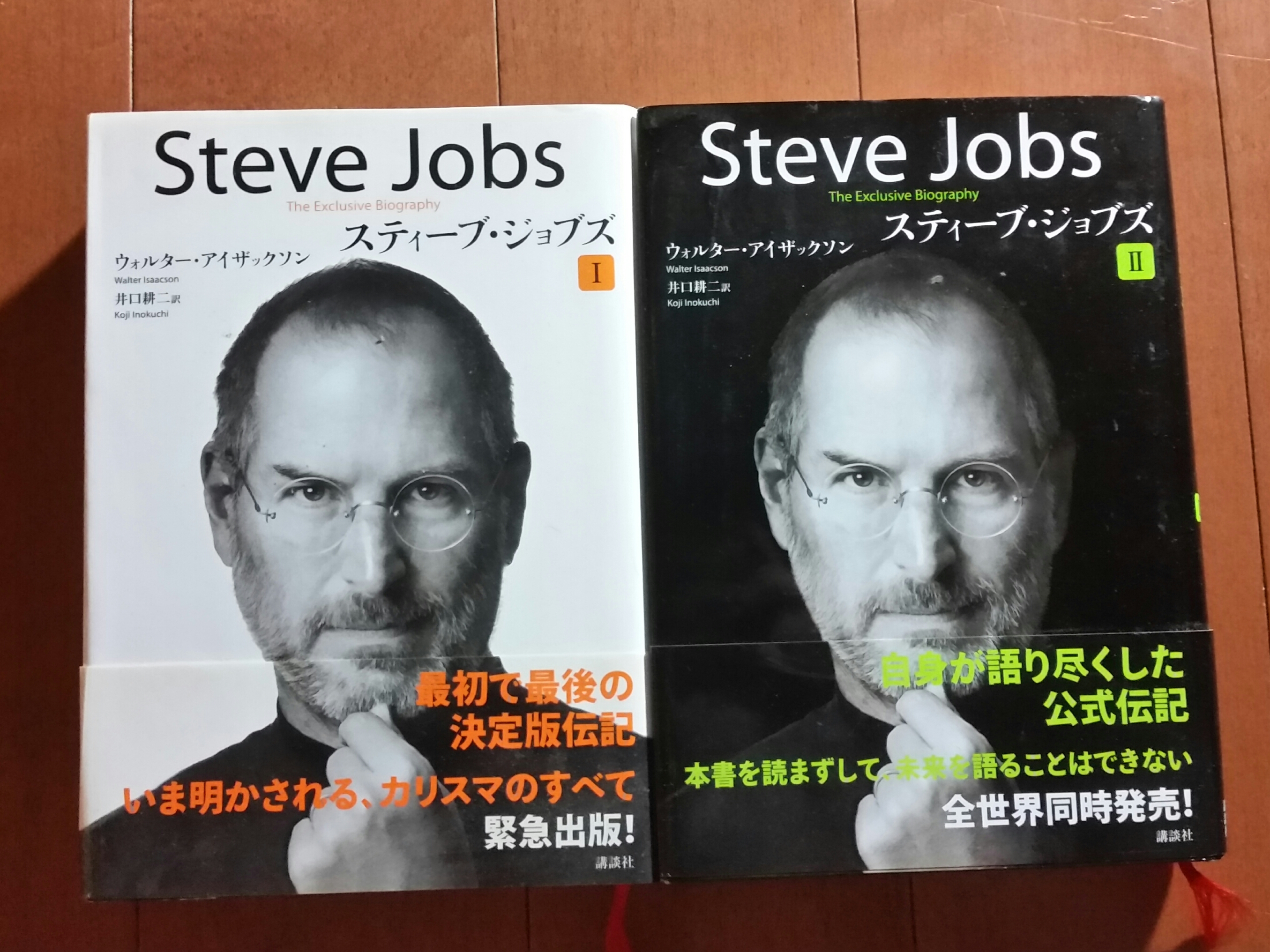 2020年5月31日
16日目:「ホモ・デウス」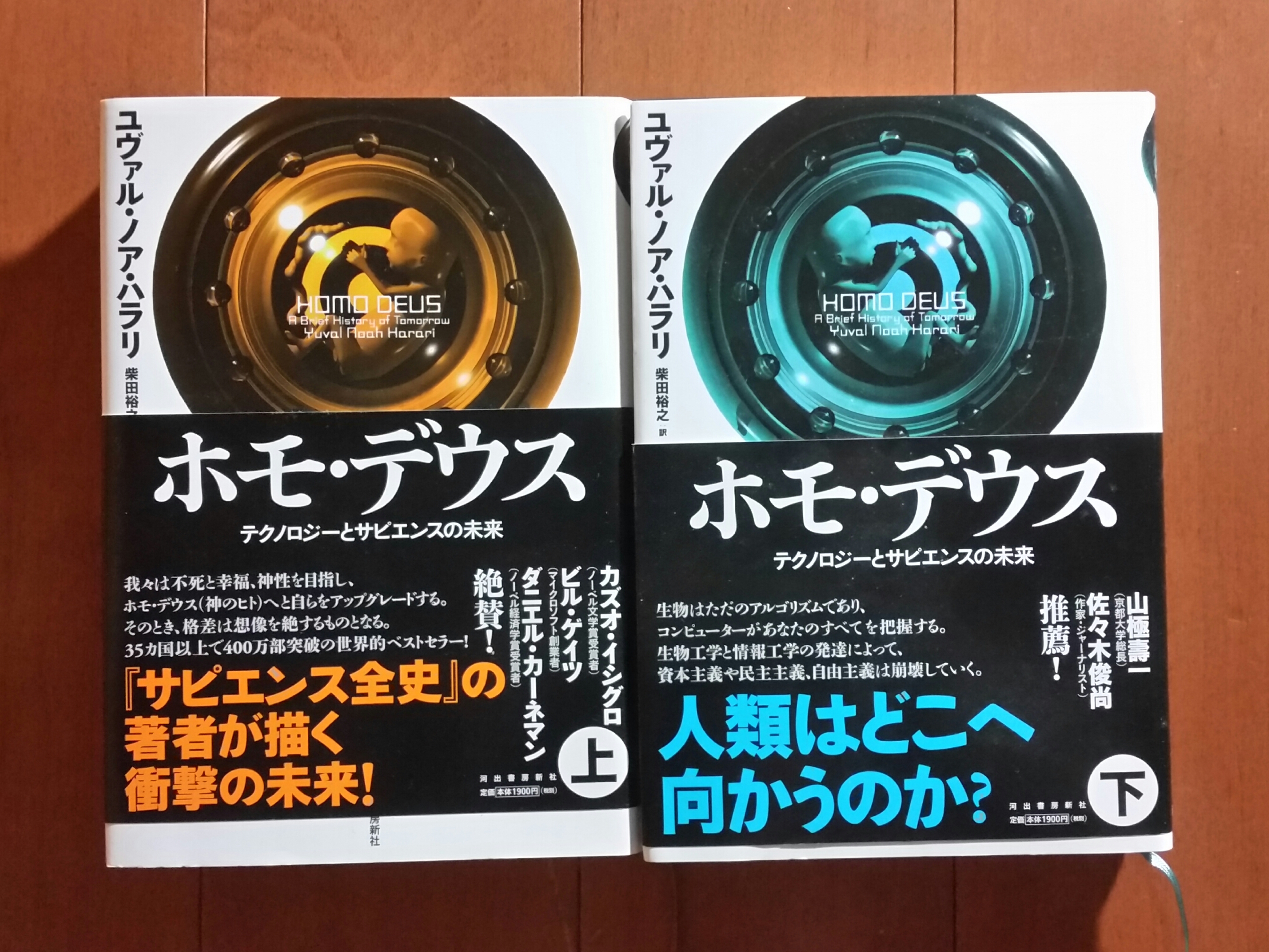 2020年6月1日
17日目:(司馬遼太郎) 海音寺潮五郎の歴史小説は、大半が調査に基づく史実だが、要所々々に主観的な独白が散りばめられていて面白かった。司馬遼太郎になると、更にドラマチックな幻想が加わる。しかも、史実と独白と幻想の境目が自然に取り払われており、歴史の中に放り込まれたような気分になる。それらは、随筆でさえ三位一体となり、あたかも先天的な記憶を呼び覚ますような代物だ。写真右は、彼のフィールドワークによる随筆のひとつ。同行した英国人ろじゃめいちんは、これはもう呆れるほど客観的で、いやぁ、困った。 2020年6月2日
18日目:「関西と関東」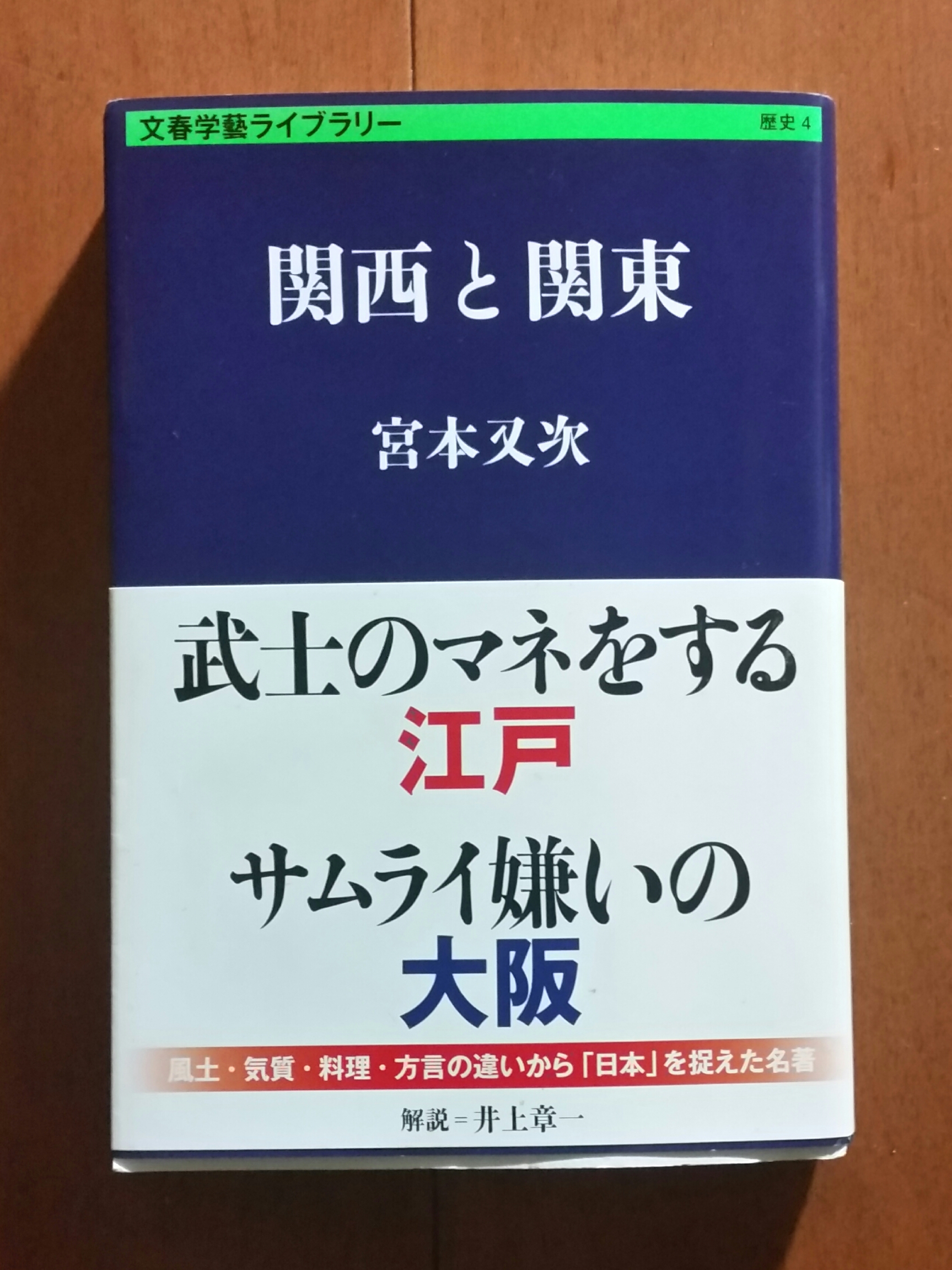 高校へ上がると関東人のガールフレンドができた。お宅へお邪魔した。「君ん家、ピアノがあるんだね!」と精一杯の関東弁で誉めた。「いま何て言った?」と彼女は笑いだした。「え?ピアノがあるねって」。僕は<ピ>の音から下降して「<ピ>アノ」と発音した。彼女は「ピ<アノ>でしょ」と言う。「<ピ>アノでしょ」、「ピ<アノ>でしょ」、口論になった。業を煮やして論破してやった。「ほんまの正しい発音は英語じゃ、ピ<ア>ノじゃ!」 2020年6月3日
19日目:「夢酔独言」 この男もどうしようもない。御家人というより無頼漢、乱暴で手がつけられない。ただ、いつも他人のために奔走している。皆に慕われ、仁侠の親分のようなところがあった。名は小吉、隠居して夢酔を名乗る。俺のような男になっちゃならねぇと戒めの回想を女房に口述筆記させたのが「夢酔独言」。けど、内容は殆ど自慢話ばかり。 子は偉かった。未曾有の内戦の戦禍が及ばぬよう江戸市中を守り抜いた軍師である。慶喜からは嫌われただろうが、頼りにもされていた。駿府にやられた徳川の残党の面倒もみた。静岡が茶の名産地になったのも彼のお陰。名は麟太郎、長じて勝海舟である。小吉とは好対称の人物だったが、その勇敢さと利他主義は親譲りと思われる。 2020年6月4日
20日目:「自分の中に毒を持て」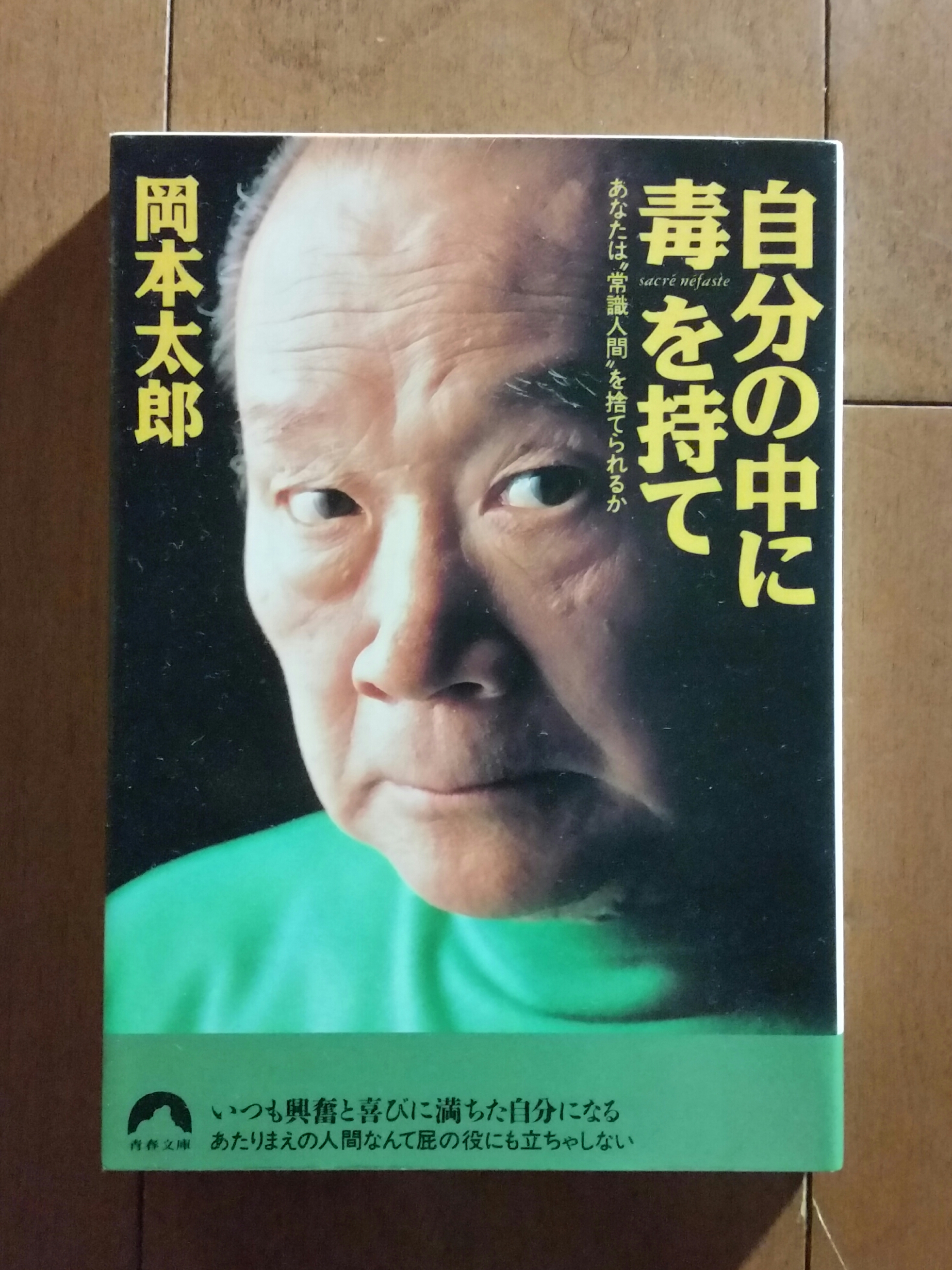 長年秘書を務め、後に養女となった敏子さんは、「芸術は爆発だ!」という本に彼の事を書いている。未知への第一歩を踏み出したとき「爆発」が起きるようだ。たとえば、晩年スキーを始め、裾野では飽き足らず、無理を言って山頂付近まで登ったことがあったらしい。周囲の警告を無視して急斜面を滑り出すが早いか頭から雪に突っ込み、関係者達が大慌てで救出したところ、彼は開口一番こう叫んだそうだ。「地球が僕に飛び込んできた!」 2020年6月5日
21日目:「選択の科学」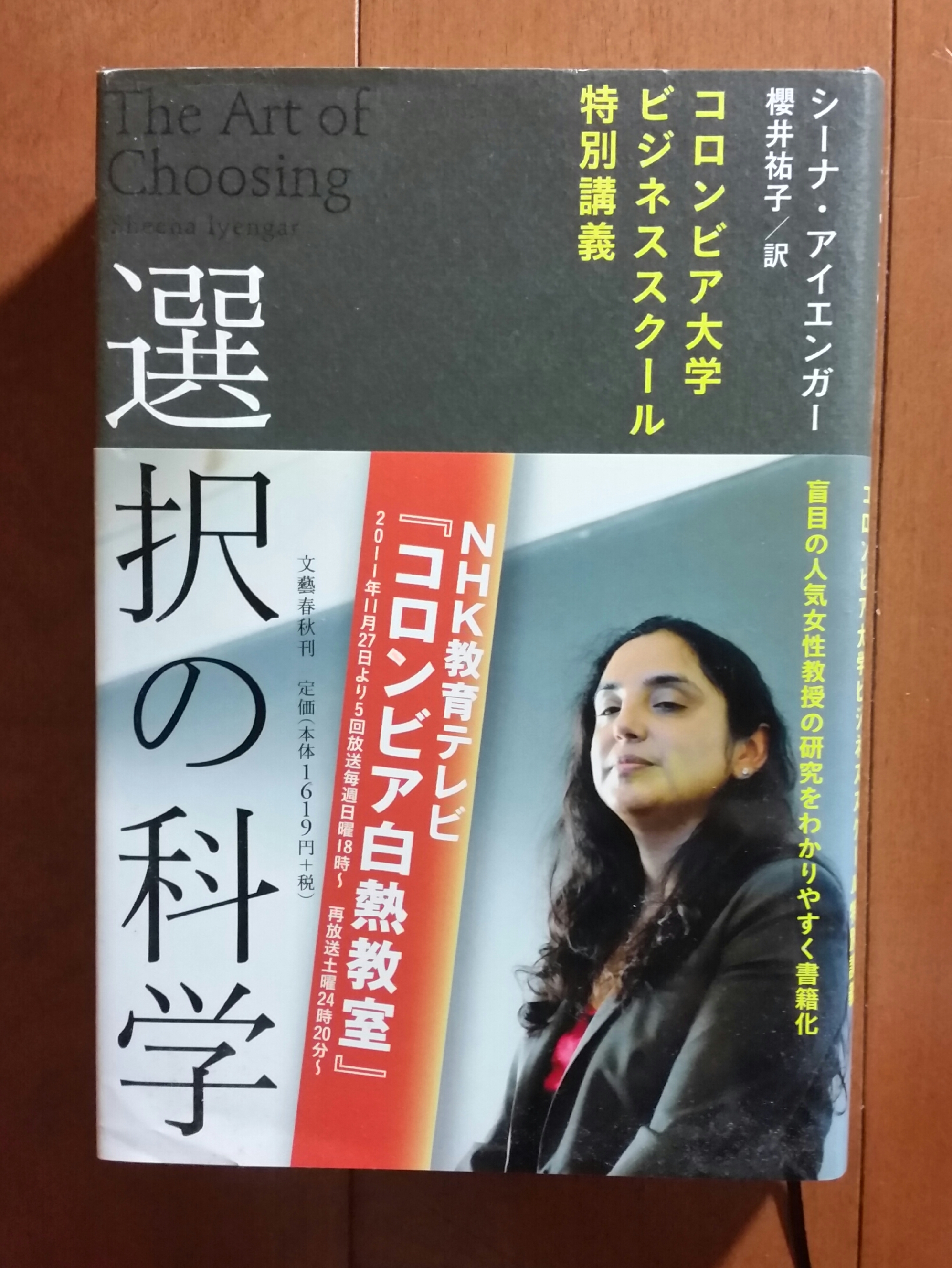 人生では、よく岐路に立つという。様々な可能性の岐路があるのだと。だが、岡本太郎氏によれば、いつも選択肢は二つ、二分岐なのだそうだ。一方は今までの延長線上にある見通しの良い安全な道、他方は先の見えない危険な道。人はそこで悩む。どう考えても前者の方が快適なのに、立ち止まる。なぜか。それは、自分が真に進みたいのは後者だからだ。だから釣り合ってしまう。そして、残念ながら、大抵は前者を選択する。 論理的な思考は、いつも見通しの良い安全な道を選択する。それが正しいと主張できるからだ。だからといって、それにどれほどの意味があるのだろう。よくよく考えれば、生きるというのはリスクを冒すことに他ならない。生きるから心配がある、危険も伴う。それなのに、我々は悩む。なぜなら、我々が真に欲するのは生きる方だからだ。だったら生きよう。 2020年6月6日
22日目:「偶然とは何か」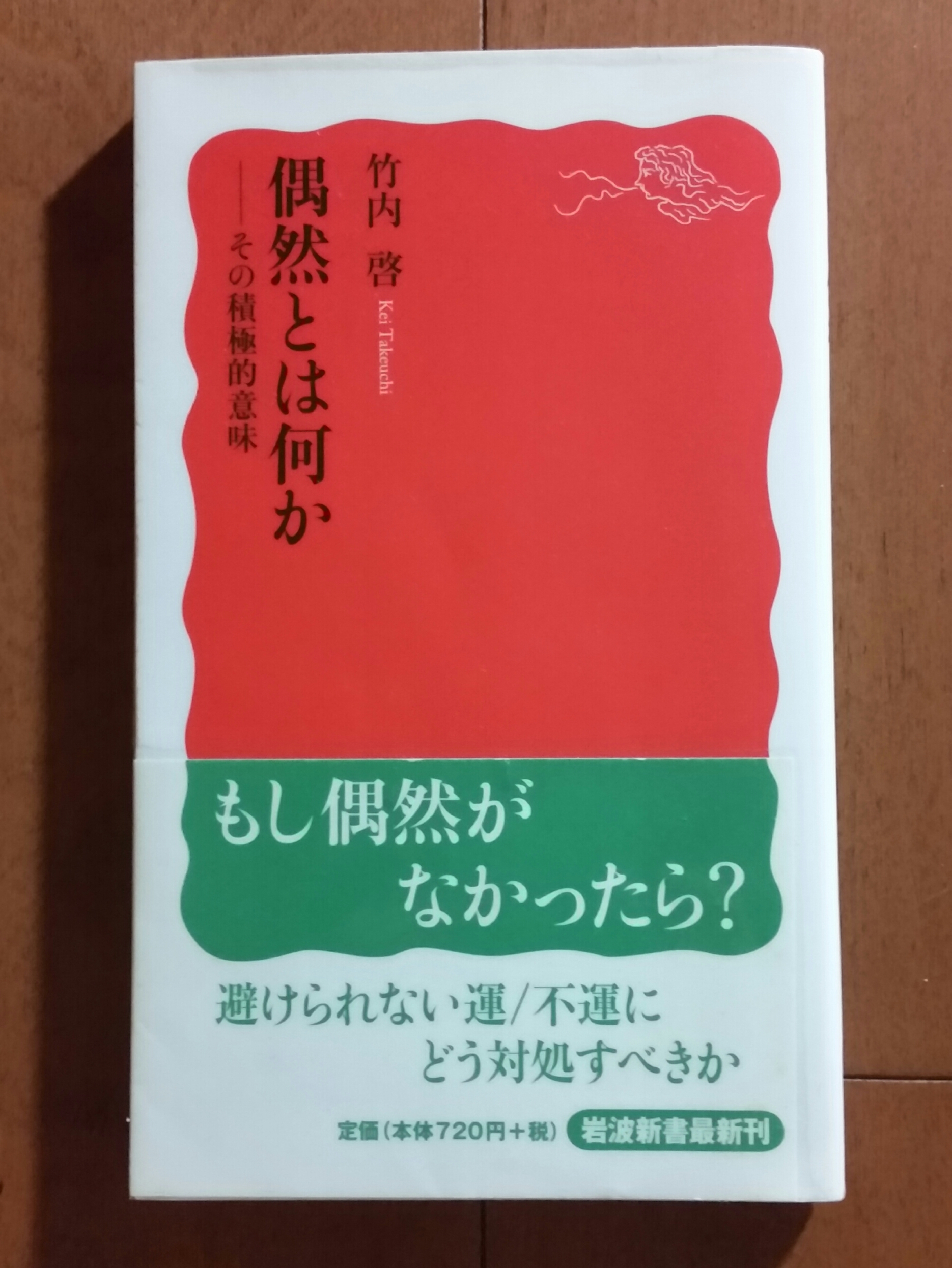 しかし、この本を読むうちに、どうやら勘違いをしていることに気づいてきた。全く異なる二つのことを確率と呼び、同じものと認識してしまっていたのだ。一つは「頻度」、もう一つは「期待」である。この二つ、主観的には因果関係があっても、客観的にはない。サイコロを1回だけ振るとき、6の目が6分の1だけ出るということはない。出るか、出ないかだ。 この違いに気づくと、幾つもの迷信が見えてくる。射幸心や絶望のメカニズムが分かって来る。頻度は、過去であり、数々の経験に基づく。期待は、未来であり、たった一度の経験である。「過去と他人は変えられないが、未来と自分は変えられるの法則」である。 「バスケットボールの神」とまで呼ばれた男マイケル・ジョーダンも、生まれついての天才ではなかったのだそうだ。高校時代は背も低く、ベンチにも入れず、毎日チームメイトのユニフォームを運んでばかりいた。努力に努力を重ねてスーパースターに上り詰めたのだ。彼のこんな言葉がある。「運命よ、そこをどけ、俺が通る」。 2020年6月7日
23日目:「生物と無生物のあいだ」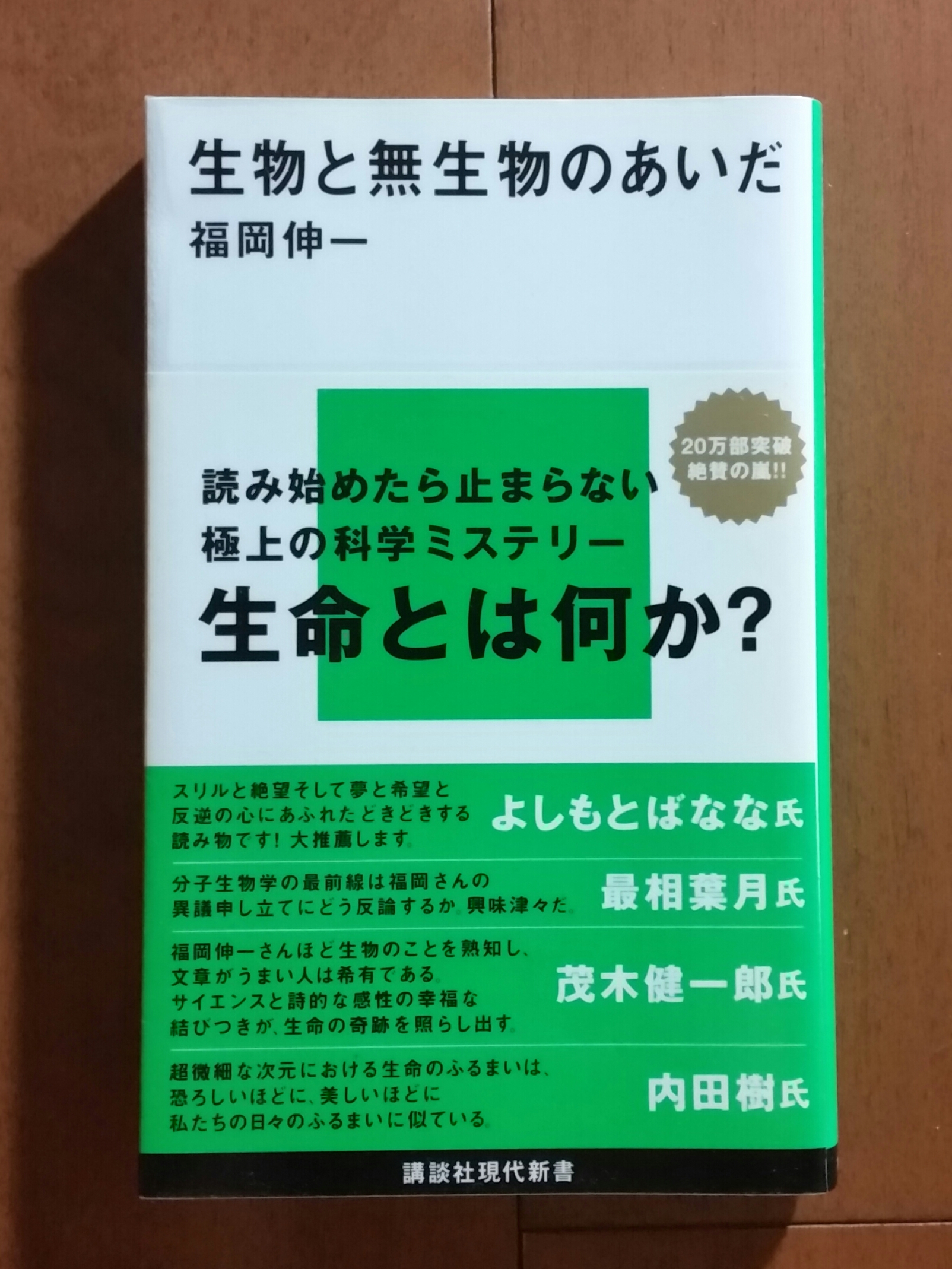 意識のあるものが生命だとするなら、前頭葉の有無で識別できるかもしれない。ただし、草木にはそれらしきものがない。それでも草木には意識はあるのだと擬人化したくなるわけだが、それはかなり乱暴だ。どうしてもそうしたいなら、次元の違う意識を想定すべきだろう。 自己複製できるものが生命とするなら、ウイルスはもちろん、ある種の有機物も生命ということになる。厳密に言うと、分子そのもの、原子そのもの、素粒子に至るまで生命ということになりかねない。 姿を維持できるものが生命だとする考え方もあるだろう。新陳代謝により、乱雑さを外に捨て、自らの秩序を保とうとするシステムだ。そう考えると、釧路湿原も、雲も、地球も、そういうシステムに違いない。太陽系や銀河系も生命ということになるだろう。もしかしたら宇宙そのものがそうなのかもしれない。 いろいろ考えられるが、大凡イメージできたことがある。おそらく生命とは、小川にできる渦のようなものなのだろう。たしかに渦はそこにある。 けれど、それを構成する水は常に流れており、一時として留まってはいない。人は、物が置いてあるようには存在せず、小川の水の渦のように存在しているのだ。さらさらと流れる水面に、渦は突如現れ、しばらくその姿を保ち、ふといなくなる。しかしまた、ふと誕生する。では、なぜ渦は誕生するのだろう。 2020年6月8日
24日目:「横浜ラブ・コネクション」 侵入できなかったかというと、必ずしもそうではない。基地ではなく駐屯地なので、さほど仰々しい境界は設けられていなかった。そもそも、本牧にあった高校への登校は運動場側からアクセスするのが近道で、そのためには居留地を横切らなければならなかった。雪が積もると米軍のガキンチョどもが大喜びで雪礫を投げてくる。頭に来るが、引っ捕らえるわけにはいかない、占領されてる側の立場だからね。夜中に忍び込んで、二人組のMP(Military Police)に追い回されたこともある。狙撃されても文句は言えなかったから、我ながらよくぞ逃げ延びたと思う。 小港にあった米軍の映画館に忍び込んだこともある。いきなり「星条旗よ永遠なれ」が流れ全員起立。米軍の一員になった気がした。しかし、一足早く観ることができた「サタデーナイトフィーバー」に字幕はなく、何を言ってるかわからない。ときおり皆「ワーッ」と歓声を上げ、「ハッハッハ」、「ヒッヒッヒ」と笑うのだが、キョトンとしているしかなかった。 パイロットの嫁さんの家に上がり込んで遊んだことも何度かある。パイロットは殆ど家に帰らないのか、ご亭主は見たことがない。7才くらいのクリスティーと3才くらいのジミーという姉弟がいて、特にジミーは僕によく話しかけてきた。英語の上に幼児語である。母親のゲイルに「彼が何を言ってるかわからない」と助けを求めると、「そうね、私もわからないわ」と笑われた。 ゲイルの弟とも仲良くなった。彼が一足先に帰国することになり、記念に早稲田祭に連れて行ってやったことがある。「ヤッキートーリ!」、「ヤッキーソーバ!」と大喜びしていた。「ヤッキー」というのは「美味い」といった意味のようだった。彼は「日本語は素晴らしい、あれはキャットじゃない、まさしくニーコゥ(ネコ)だ」と感心していた。如何せん別れ際「ありがとうナウキ、楽しかったよ」と言う。怪訝に思って僕の名前のスペルを言わせると"NAUKY"だろうと言う。そうじゃないと説明しながら、なんだか映画「ブッシュマン」のニカウさんになったような気がした。 その他、米軍子女たちとよく遊んだ。新しくできた元町のロック喫茶なぞで知り合うのだ。ハーフが多く美女も多いのだが、口が汚いという共通の欠点もあった。たとえば、石川町をとぼとぼ歩いているとき、車に箱乗りして通りかかったアイリーンに大声で「ヘイ、ナオキ!今日ウ○コした?」と挨拶されたことがある。完全無視、他人を装った。あとから不平を言われた。 日本人の友達は、変わり者とヤンキーが多かった。当時、奈良の不良は、男子がロン毛でベルボトム、女子がロン毛でミニスカートと相場が決まっていたのだが、横浜は対称的だった。男子がリーゼント(正しくはリージェント)でボンタン(ニッカポッカのようなダブダブのズボン)、女子はパーマ頭でロングスカートだった。奈良が米軍子女風、横浜がコリアンタウンの若者風だったというのは興味深い。当時のヤンキーが昨今と少し違ったのは、正々堂々を美学としていたところだろう。源平合戦の武士のようなところがあった。もちろんヤバイのもいたが、概ね純情だったような気がする。 昨今は、横浜に出掛けても、当時の感慨がない。奈良に帰ったときもそうだった。もちろん、名所旧跡は残っているし、数々の文化も引き継がれているだろう。自分自身の感性が衰えたのか、空気が入れ替わったのかはわからない。ただ、このコミックスを開くと、あの頃の横浜の空気がパァーっと溢れ出てくるのを感じる。 2020年6月9日
25日目:(喫茶店) 時には知り合いに遭遇したり、仲間で集ったりすることもある。お喋りに興じることも、談義、討論に及ぶこともある。喫茶店によっては、親い仲間が集いやすいよう、クラシック、シャンソン、あるいはジャズなど一定の嗜好の音楽を流したり、古典派、印象派、あるいは現代派など一定の嗜好の美術品を置いたりする場合もある。 元来、横浜の中心地というのは、その名の通り「関内」の辺りであり、代表的な歓楽街は伊勢佐木町界隈であった。いわゆる接客サービス付きの飲食店が軒を並べる中、「ダウンビート」というジャズ喫茶があり、黒い箪笥のような大きなスピーカーでモダンジャズを掛けていた。日の出町まで足を伸ばすと「グッピー」というロック喫茶があり、生演奏も行われていたと聞く。大学に通うようになると、渋谷の百軒店にある「ブラックホーク」というロック喫茶に通った。レゲエミュージックばかりが掛かっていた。 ある日、悪友から誘いがあった。元町にジャズ喫茶ができるから手伝いに来いという。行ってみると、改装直後の匂いのする壁全面にビバップやモダンジャズの巨匠たちが描かれていた。テーブルを運んだり椅子を並べたりしたあと、開店祝いに参加した。元町の「ミントンハウス」である。立ち上げの中心メンバーは、プロカメラマンの菊地さん、慶大中退のフリーター木原さん、そして店長になったオイドン(本名不詳)である。 その木原さんが雇われマスターをしていた雀荘を買い取り、潰して、ロック喫茶を立ち上げた。屋号は「マギーズファーム」。当時のジャズ喫茶やロック喫茶は大凡暗くて黒が基調という印象があったが、そこは白木張りの明るい部屋で、観葉植物が置かれ、後に複数の大会でダーツの日本チャンピオンを排出することになるダーツボードが設置された。 主にウエストコースト・ミュージックが掛かっていた。黒が基調のブリティッシュ・ロックに傾倒していた自分にはとてもロックと思えなかったのだが、多感な年頃である、次第に感化されていった。ただし、この手の店は客が固定化されていく。フェリスのお嬢様方が立ち寄ることはあっても、リピーターは少なかった。もっぱら顔見知りが集うことになり、匿名の空間は消滅し、一見客は疎外感を味わい、一層入り辛くなる。長くはもたなかった。 その頃からではないだろうか、レコードを掛けるだけではなく、生演奏を楽しめる店が増えていった。本来の「カフェ」の代表的な一様式もそうだという。いわゆる「ライブハウス」だが、これはどうも和製英語、ネイティブな英語圏の人はホラー映画「ホーンティッドマンション」のようなものを連想するらしい。なるほど直訳すれば「生きてる家」である。あちらでは「ジャズ・バー」とか「ロック・クラブ」といった呼称が一般的なようだ。けれど、悪いジャポニッシュだとは思わない。「生きる家」、「命の家」である。人と人が垣根をなくして一体になる一時を提供する。 我が国は、中国から文化を学び、西洋から文明を学んできた。だから、漢字とカタカナには滅法弱い。「ソーシャル・ディスタンシング」と聞けば、ありがたい故事成句のように奉る。そして盲信する。けれど、テレビでパックンが言ってたが、米国では既に言い直されているらしい。「フィジカル・ディスタンシング」と言うそうだ。今必要なのは肉体的な距離であり、社会的な距離でも精神的な距離でもないのだから。 2020年6月10日
26日目:「村上海賊の娘」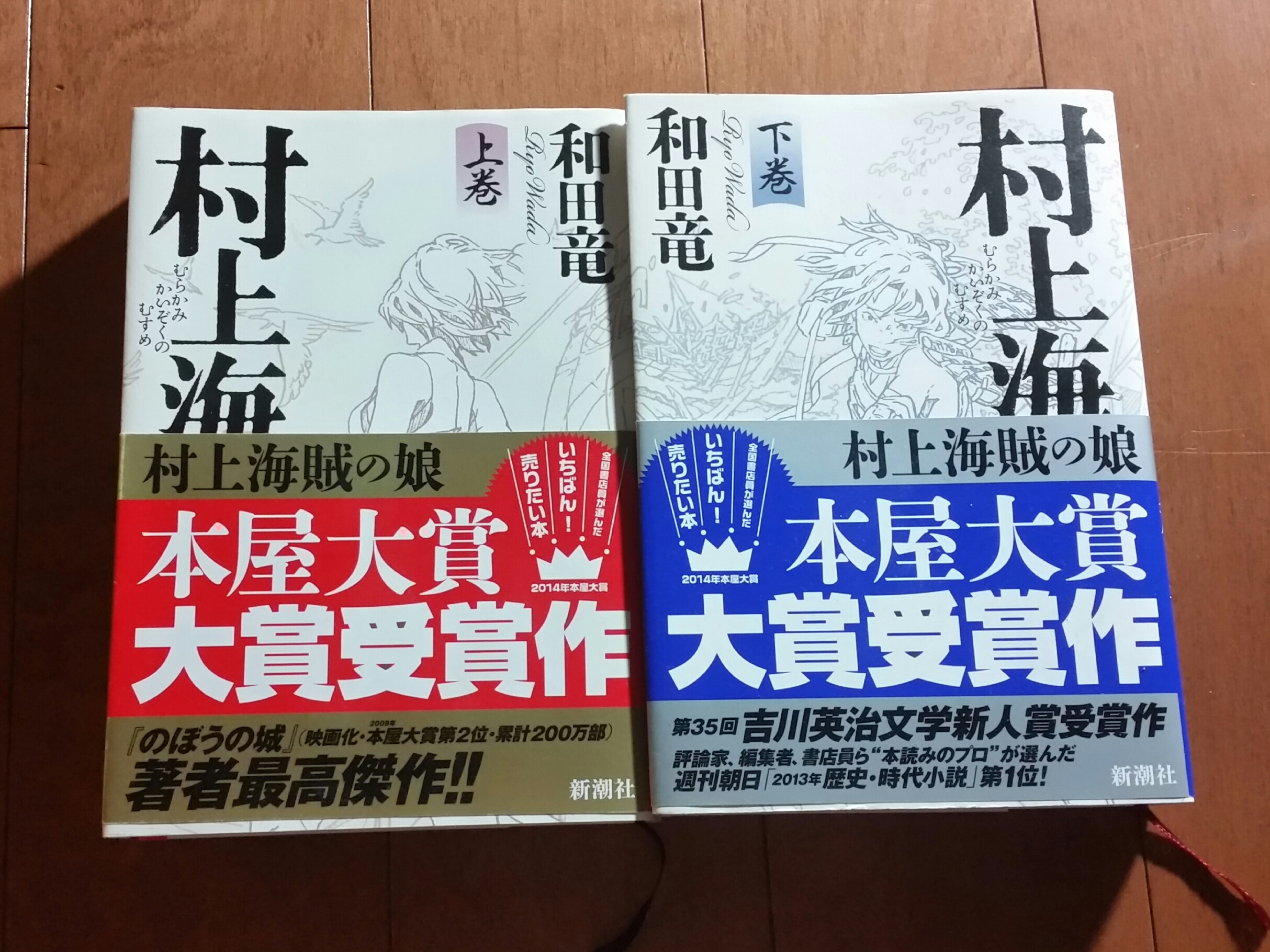 同行したイベントで憶えているのは、映画館に「スターウォーズ」を観に行ったことくらいか。第一作「エピソードⅣ」のロードショーで、すっかり心奪われてしまった。後に知ったことだが、監督のジョージ・ルーカスは黒澤映画にかなりインスパイアされていたらしい。そう言われればチャンバラ映画だし、銀河の騎士「ジェダイ」は「時代劇」から捩った言葉らしい。 これも後に知った話だが、時代劇の「時代」とは、日本の古い時代という意味ではなく、歌舞伎狂言的演出から脱却した新時代の映画といった意味だったそうだ。とはいえ、「時代小説」という言葉には、現代ではない過去の日本を舞台にした小説というニュアンスが強い。ただし、山本周五郎や藤沢周平の作品には、江戸時代のような舞台設定を利用して、まさに現代の可笑しみ、悲哀、感慨、不条理が綴られているから、そういう意味では新時代的小説なのかもしれない。 一方、「歴史小説」というジャンルもある。これも小説でありフィクションには違いないのだが、確たる伝承もない市井の人物を中心に話が展開する時代小説とは嗜好を異にし、一般的な史実を元にしている。そこに様々な新解釈や空想が織り込まれて小説としての魅力が備わるわけだ。その意味で、司馬遼太郎の代表作の多くは歴史小説と呼ばれているはずだ。もちろん、彼独特の作風は比類ないわけだが。 和田竜の「村上海賊の娘」は、上記のような意味からすれば、やはり歴史小説の書棚に入るのだろう。なので、どうしても比較してしまうのだが、司馬作品を黒澤明の映画とするなら、三谷幸喜の映画のように感じられた。綴られた寸劇や話のリズムがそう連想させたのだろう。また、司馬作品をスターウォーズの「エピソードⅣ」とするなら、「エピソードⅠ」を感じさせた。アクションシーンの比重がそう連想させたのだろう。 読み終えるのにけっこう体力を要したが、「本屋大賞受賞作」というのが嬉しい。これは全国の書店の投票で決まる賞で、一部の「有識者」の胸先三寸で決まるわけではないからだ。ネット社会の隆盛とパンデミックのおかげで多くの本屋さんは苦境に立たされているかもしれないが、こうした紙の冊子と本屋大賞には「永遠なれ!」とエールを送りたくなる。今年はどの本が受賞するのだろう。早見和真の「店長がバカすぎて」あたりか? 2020年6月11日
27日目:(杉浦日向子の漫画) 漫画の場合はどうだろう。第一人者の手塚治虫が、本当は映画を作りたかったがリソースがないから漫画を描き始めたといった旨を語っていたように記憶している。頭の中にある物語をシンプルな絵で伝え、読者の想像力を借りてその世界を映画のように再生してもらうわけだ。なるほど、手塚漫画を読んでいる間、我々はそれが漫画であることを忘れ、彼が提供してくれたストーリーを体験する。漫画もまた、ストーリーの媒体なのだ。叙情的な描写もなくはないが、あっても息抜きやアクセントという場合が殆どで、それが主役になることはない。 ところがだ、少なくともこの漫画家は違った。むしろストーリーが脇役であり、主役を務めるのは叙情なのである。その叙情がまた曲者だ。どこか既視感を抱かせるような、意識の裏に眠る大海から記憶を呼び醒ますような叙情である。杉浦日向子という方の漫画がそうだった。 初めて目にしたのは何れかの週刊もしくは月刊のマガジンで、数々の他の漫画に紛れて掲載されていた。意図せず読み進んで、呆気にとられた。他の作品とは一線を画し、悪く言えば尻切れトンボなのだが、えもいわれぬ感慨を胸に残す。また読みたいと期待したが、彼女の作品はあまりコンスタントには掲載されていなかったようで、やがて遭遇しなくなった。いまこうして単行本で固め読みしてみると、一つ一つの話にさしたる展開はないのだが、全体として何か大きなストーリーを携えているような気がしてくる。ただしそれは、意識的・論理的なものではない。もしかしたら、叙情というのは、言葉を超えた別次元のストーリーなのかもしれない。 僕は音楽が好きで、特に歌ものが好きなのだが、メッセージソングには殆ど気持ちが向かない。意識的・論理的な歌詞に都合のいいメロディと調子のいい拍子を着けたところで何が面白いだろう。むしろ、耳に憑き、邪魔である。やはり、音楽や歌の主役は、叙情ではないだろうか。彼女の漫画には、どこか音楽や歌に相通じるものがあるように感じる。 2020年6月12日
28日目:「一日江戸人」 日本との出会いは、太平洋戦争の折、海軍の情報士官として捕虜あるいは戦死した日本兵の日記を否応なく解読する業務であったようだ。米軍は機密情報漏洩を防止するため日記を禁止していたが、日本軍は士気高揚と検閲のため日記を奨励していたのだ。なるほどそれらには、皇国に報いる青雲の志や、壮烈ナル総攻撃ヲ敢行スルといった威勢の良い文言が記されていた。しかし、並走していた仲間の軍艦が目の前で撃沈されたり、負傷して潜伏したジャングルで病魔に犯されたりすると、内容は個人的になり、素直な心境や、残してきた家族への想いといったものに変化していったのだそうだ。 これを拾った者は故郷の家族に届けてほしいといった走り書きのある日記まであったという。名もない一兵卒の日記は、文章の上手い下手はともかく、極めて文学的な色彩を帯び、心を揺さぶられずにはいられなかったという。 彼の著書は数多遺っているが、「百代の過客」(はくたいのかかく)と「続・百代の過客」は、日本人の日記を扱った傑作だ。 我々にはとても解読できないような古文も含め、膨大な日記を読破した能力と労力だけでも驚嘆に値する。それにしては不思議なことに、何年経っても彼が喋る日本語は覚束なかった。片言の外人風なのだ。もしかしたら、彼は左脳(論理脳)以上に右脳(感性脳)で日本を捉えていたのかもしれない。例えばこんな文面がある。 >>> 弁内侍(べんないし)というのは、まことに人をひきつけてやまない女性である。早くもこの日記の初めの方で、私の心をすっかり捕らえてしまう。寛元四年(1246年)11月17日(この日記は、他の宮廷女性の日記に比して、はるかに日付が厳密である)のこと、作者は吉田神社の祭礼の使いにたたされる。その帰途、妹が仕えている女工所(にょくどころ)を急に訪ねてみたくなり、車を曳く者にそちらの方へ行くように命じる。ところが車の供をしていた蔵人(くろうど)が、夜も更けているゆえ、廻り道は致しかねると断る。だが自分のしたい通りにするのだと心に決めていた弁内侍は、吉田の使いに立ったものは、帰りにそこへ寄るのがきまりになっている、と言いつのるのである。 「きまり」というのは、内侍がとっさに考えついた作り事だったが、供の者は、「まことにさる先例ならば(ぜひなし)」などと言いながら、彼女の意に従う。だが女工所に着いたときには、夜もいよいよ深まって、衛士が門をなかなか開けてくれない。そこで今度は供の者が、吉田の帰りには内侍がここへ立ち寄るのが決まりになっている、それだのになぜ門を早く開けぬか、と衛士を叱りつけるのである。内侍は言っている。 かやうの事や先例にもなり侍らむとをかしくて(このような事がいわゆる先例というものになってしまうのであろうと思いおかしくて) 日本人の好きな「先例」に対する皮肉が、これほど魅力的に表現された例を、私は他に知らない。 <<< 膨大な量に及ぶ他人様の日記など、到底読破できるものではない。くずし字の古文や漢文となれば尚更だ。ましてやニューヨークに生まれ育った彼にとって、言語的にも地理的にも時代的にも、それらは大いに隔たりのある文書のはずである。けれど彼は、その時空をさっと飛び越え、作者にそっと寄り添ってしまう。東日本大震災を機に、89歳にして日本に帰化し、96歳の天寿を全うした。時空を超越する圧倒的な自由を持った方だったのだ。 さて、杉浦日向子の漫画を目にしなくなって何年か後、彼女はテレビ番組に現れた。「お江戸でござる」という芝居小屋仕立てのコメディで、舞台の後、「先生」と呼ばれる彼女が時代考証や江戸に関する蘊蓄を披露する。先生にしてはうら若い美女が恐ろしいほど江戸文化に詳しいので目を見張ったり舌を巻いたりしたが、それは単なる知識量ではなかった。 写真のブックカバーは、いわば江戸案内の書である。おそらく背景に相当な調査があったのだろう。そこで得られた数々の点が、線で繋がり、面を形成して、このような立体的な案内が生まれたのだと想像する。だが、もはや三次元では収まっていない。少なくとも四次元時空が現れており、どうみても彼女は江戸時代からタイムトラベルしてきたんじゃないかと思えるほどのリアリティなのである。彼女もまた、時空を超越する能力を持っていたのだろう。 2020年6月13日
29日目:「杉浦日向子」 特筆すべきは「隠居」後の大活躍だ。藤沢周平の「三津谷清左衛門残日録」ではないが、「日残リテ昏ルル二未ダ遠シ」であり、しかも彼女は未ダ十分二若シである。執筆を中心とした文芸活動が次々と花開き、満開の季節を迎えた。惜しむらくは、やがて下咽頭癌を発症し、46歳の若さで他界されたことだ。 一昨年、彼女の生誕60周年を祝し、深川江戸資料館でイベントがあるというので覗いてきた。館内は、粋な風情でありながら、なんとも清廉な空気に満たされていた。いわば縁もゆかりもない自分を「ようこそお出でくださいました」と迎え入れてくれているようにも感じられた。会員しか参加できないという別室の講演を、時代劇よろしく、入り口の脇に隠れて傍聴した。 この冊子は彼女の還暦を記念して発行されたもので、本人の対談、本人の漫画作品、そして縁の方々からの寄稿により、彼女が今も我々の心の中に暮らしていることを教えてくれる。 2020年6月14日
30日目:(呑々BOX三部作) 焦土から立ち直った日本人ならV字回復するだろうとの楽観論もあったが、もはやそんな気骨のある人材なぞ多くは残っていなかった。平成不況は、大恐慌という形ではなく、蛙を煮るぬるま湯のようにやってきた。昭和の時代、青島幸男が作詞してクレージーキャッツが唄った「そのうちなんとかなるだろう」のようには行かなかった。不況が日常となり、人々は既得権益にしがみつき、先例主義、現状維持が「常識」となった。ただし、表向きには安定し、ある種の太平の世でもあった。その方法の是非は別として、戦禍にまみれることもなかった。いわば「昭和元禄」に続く「平成享保」のようなものだろう。 昭和の時代から、時代小説に対して現代小説というジャンルを扱う「小説現代」という雑誌がある。平成バブルが弾けた後、そこに妙な連載が始まった。「東京イワシ頭」と題されている。「鰯の頭も信心から」のあのイワシである。なんと、杉浦日向子の随筆だった。こざっぱりした印象の杉浦とは真逆のターゲット、いかがわしい健康療法、高級エステ、新興宗教、ディナーショー、ストリップ劇場といった、キッチュかつ謎めいたシアワセ商法に突撃取材するという立て付けだ。よくぞこんな取材をと不思議に思ったが、杉浦の背中を押してくれるものがあったのだろう。その一つが、専属の編集担当となった新入の女子社員であったことは間違いない。 杉浦は、その担当に「ポアール・ムース」(洋梨の卵白泡菓子)という渾名を与え、部活の後輩のように可愛がった。文中では「ポアール」とか、単に「ポ」と呼ぶほどで、大いに親しみを感じている。実務的で手抜かりのない担当より、大学を出たばかりで西も東も判らない純朴さを気に入ったのかもしれないが、けっこう「ポ」からインスパイアされているところを見ると、これは馬が合ったと見るべきだろう。杉浦は、全ての回に「ポ」のイラストや漫画を掲載している。 イワシ頭は三年ほどで連載を終えるが、その余韻醒めやらぬまま、「呑々草紙」という次の連載が始まっている。主題がイワシからお酒へとシフトしたのみならず、行動範囲が東京を飛び出して日本全国へと広がっている。杉浦は元々出不精だったというから、やはりこの行動力の裏には背を押す存在があったはずで、お供はもちろん「ポ」である。イワシではあまり印象がなかったが、呑々ではフッと我に帰る瞬間があって興味深い。例えば祭のたけなわで帰りの便のタイムリミットを告げられ、「孵化に失敗したコオロギ」のような寒さにゾッとするくだりなど身に詰まされる。列車に乗るとすぐ眠りに落ちてしまう「ポ」の寝顔を前に、遠い初キスのことを回想し、それがラッキョウの味だったことを悔いながらビールを飲んでいるシーンも染みる。「ヒ」と「ポ」の「コンビ」は、まるで仲の良い姉妹のように次から次へと旅を重ねていく。 呑々は二年ほどで終了し、「入浴の女王」という連載が始まった。全国から関東一円へと徐々に行動半径が戻り、イワシの無茶や呑々の破天荒からは幾分落ち着き、話もある程度定型化されてくる。もしかしたらだが、この頃には多少の体力的な自制があったのかもしれない。それでも内容は実に味わい深く、老舗の銭湯巡りを中心に、様々な気付きや逸話、舞妓さんの裸体描写まで登場する秀作だ。訪れた銭湯と「ポ」の姿が毎回欠かさず挿し絵として描かれ、遂に最終回ではサービスショット(ヌード)になっている。それが、なんとも微笑ましく、我が子の晴れ姿を撮った写真のようにさえ感じられる。広告用に作成されたテレホンカードに写っている「コンビ」は、まるで若母と愛娘のようにも見えてくる。 ※たいしたナニではないのですが、明日から一週間そこら手術入院する運び、このチャレンジは今回でお開きにしようと思います。(っちゅうか何日やっとんねん!) ってことで、このエッセイは病院で編集中。 昨日、眼の手術、怖かったですが、なかなか幻想的、 目ん玉の宇宙を堪能した初体験でした。 病室は四人部屋が貸切り状態で快適だったんですが、 今日になって向かいにも隣りにも患者さんがやってきた。 漏れなく奥様が付いて来てあれこれ仰るし、 患者は高齢で耳が遠いですから看護師さんも大声、 引っ越し先の新居か幼稚園の遠足のような賑やかさで 五月蝿いの五月蝿くないの。 ようやく奥様連中が帰って静かになったかと思いきや、 独り言、大オナラ、大イビキ、 ラジオだかテレビの音(耳が遠いから大音量にして イヤホンから椋鳥の口喧嘩のような音をだだ漏らせたまま 本人は転た寝して大イビキをかいているという忙しさ)、 それにも増して時々息が止まりそうな寝息が気になる。 こりゃなんとか早く治って早く退院させてもらわんと!
   
--- 2020/5/10 - 6/17 Naoki |

